試験は難しいが、合格したら自分の人生が変わるほど大きな価値のある『国家資格』
その中でも受験資格がなく、なおかつ価値としてそこそこ高い宅建(宅地建物取引士)や行政書士などの士業は人気ですよね。
宅建は実際に不動産関係に勤めることができ、引く手数多の資格で独立も全然夢ではないですし、行政書士は就職は少ないにしろ、地方によって違いますが、30万ほどの初期費用があれば自宅開業もできる資格で、初期投資が少ない分大きなリスクを負うことなく始められる職業です。
しかもこれらの資格は、使わずとも持っているだけで評価されます。
僕は今のところ行政書士をまだ活用できていないのですが、行政書士合格者の肩書きはとても有効なハロー効果を与えてくれます。
ハロー効果:資格を持っていたり肩書きがあったりなどの表面上の特徴で、その人の評価を通常よりも高めてしまうこと
そんな人生を変えてくれるほど大きな価値のある国家資格だからこそ、試験自体は簡単に合格できるようなものではありません。
今回はそんな宅建と行政書士を、僕が独学で合格した時に行っていた学習法・習慣を公開します。
少し長くなるかと思いますので、いくつかのパートにわけて数記事で紹介していきます。
ちなみに僕は、宅建は3ヶ月、行政書士は5ヶ月半ほどの学習期間で合格しました。ネットでの合格者の声をみている限り、結構最短に近い勉強期間ではないかなと思っています。
ですが、僕自身決して勉強が得意なわけではなく、お恥ずかしい話ですが高校時代120人中、下からベスト10の知力でした…。
そんな僕でも合格できた学習法ですので、それが合う人もきっといるかと思います。
参考にしていただいて合格できる人が増えてくれたらとても嬉しいです。
ちなみに今回の学習習慣法は、あくまで習慣や考え方などの面をピックアップしています。
どのような勉強をした方がいいかなどの試験対策に特化したものではありません。
もしもそのような試験対策のことを知りたい場合は、それに精通した行政書士やスクールが公開しているブログ、もしくはスクールに通うことをオススメします。
例えば下記のオンライン学習サイト『資格スクエア』は、【eラーニングサービス】を活用し、スマホやPC、タブレットがあればどこでも隙間時間で勉強できるオンラインスクールです。
やはり時間にシビアな社会人や、日中は勉学に励んでいる学生、家事育児、中には仕事までこなしている多忙な主婦にもオンラインで、しかも隙間時間で視聴できるeラーニングはとても扱いやすいサービスですよね。
資格スクエア
あとは少し珍しいのですが、働く女性や主婦にフォーカスした【SARAスクール】という通信講座サイトもあります。
占い、美容、健康、片付け術など女性の受験割合が多い資格をたくさん扱っており、国家資格も宅建はないのですが、行政書士は扱っていました。
この資格スクエアやSARAスクールだけに限らず、他にも様々なオンラインスクールや講座購買サービスなどもありますので、自分に合うと思う勉強の仕方を見つけてください。
それでは本題に入っていきます。
※今回掲載する学習習慣法は、合格を保証しているわけではありません。

1:参考書は図やカラーに富んでいるものを選ぶ
僕が宅建の時も行政書士の時も参考書選びでポイントとしたところは、図を多く使われていることや、色使いが多い参考書です。
人は文字のみよりも、わかりやすい図で表している方が記憶しやすいので、文字だけではわかりにくそうな箇所は適度に図で表している参考書がオススメです。
極端な例で言うと、漫画と小説では同じ内容でも漫画の方が鮮明に記憶されますよね?その時の場面であったり、文字であるキャラのセリフの部分すらもしっかり覚えてます。
ですので、僕はまず初めに文字が多い参考書から手を伸ばすのではなく、漫画系の参考書から始めるのがいいかと思っています。
 |
 | 【中古】 マンガでなっとく!!行政書士をまるごと理解 / 武田 伸輔, 小橋 健二 / 東京法経学院 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】 |
覚えやすい漫画系で大まかな要点を掴み、参考書でもっと細かく覚える。
いきなり参考書の文字ではなく「あっ、あの時の漫画で書いてあった」から入る方がインプットしやすいと思います。
実際僕も漫画系の参考書から始めて要点を掴む、そして一番ボトルネックな、無知である入り口を楽しく通過するやり方をしていました。
上記や下記の参考書はどちらも人気の漫画系参考書です。是非参考にされてみてください!
 |
 | 【中古】 マンガはじめて行政書士 民法 マンガでわかる資格試験シリーズ/植杉伸介【著】,井上のぼる【画】 【中古】afb |
2:勉強するのが苦手というバイアスを無くす
人は誰しも様々なバイアス(思い込み、固定概念)に縛られているもの。
それは勉強なども一概には言えず、「学生時代、頭が悪かったから」「あなたは物覚えが悪いと言われたから」「集中力がないから…」などの理由で、自分は勉強が苦手だ、きっと長時間の勉強などできない!などと思い込んではいませんか?
実は何らかの先天性な理由がある人を除き、人は誰しも物事に集中する力を持っています。
ですが僕自身も、勉強が苦手、集中力なんて皆無だ!というバイアスに囚われていました。
そんなバイアスを無くすために行った簡単な方法が、実はあります。
その方法とは『とりあえず5分だけ参考書を読む。から始める』ことです。
これだけ聞くと「??」でしょう。詳しく説明していきます。
集中力がない、勉強が苦手だという意識のある人は、とにかく挫折する確率も高いです。そんな意識の中まだまだ無知な状態で難しい専門用語をいきなり覚えようとするわけですから、それは当然のことですね。
その状態の中「1日4時間の勉強をしよう!」「集中して2時間勉強して、30分休もう」などと、結構ハードなスケジュールを組んだところで挫折の確率を上げてしまうだけです。
ですので、試験まであと1ヶ月!など勉強期間が圧倒的に足りないなどの例外を除き、前述した『とりあえず5分だけ参考書を読む』から始めてください。
5分取り組んだら、20分でも30分でも好きな時間をとってください。
ゲームをするでもいいですし、漫画を読むでもいいです。とにかく勉強時間を取ると叶えられなくなる欲求を叶えてください。
5分だから簡単ですよね?その後は自分のしたいことができるわけですし、5分くらい全然頑張れるかと思います。
ですがこれを繰り返し続けていくと、驚いたことに5分だけじゃ足らずもっと集中して続けられるようになります。
5分だったのが10分に、15分に、30分にと長くなっていきます。
これは『勉強を始める』という狭い入り口を、苦なく入りやすくすることによること、そして少しずつでも読み始めると理解度が徐々に高まるので、もっと知りたい欲が高まることにあると思っています。
それに参考書や問題集が進んでいくと、見開き1ページの内容をしっかり読んで把握するのにも5分以上かかるようになってきますから、数ページ読むだけで15分と過ぎていたなんてことは当たり前にあります。
実際に僕もこの方法をしてみて、最初から無理なく資格勉強に取り組めるようになりました。
最初の1ヶ月はこれを続けて集中して勉強ができる時間を伸ばして、2ヶ月目からは1時間の集中、5分の休憩を繰り返しできるようになりました。
僕のように苦手意識がある人がこの手順を間違えて資格勉強に取り組んでしまうと、結構な確率で挫折します。
そんな甘えたやり方で大丈夫か…?なんて疑問に思うかと思いますが、人は鞭を打たれながら始めるよりも、甘い飴を舐めながら始める方が楽しく苦なく、またその勉強自体を好きになっていけると思っています。
騙されたと思って是非参考にしてみてください。
3:一旦寝るは記憶に効果的?
これは有名な話なので、もしかしたら知っている方もいるかもしれません。
実は勉強をするのに最適な時間帯は、就寝前の時間帯なのです。
これは実際に実験もされているのですが、テスト前に勉強をしてテストを受けるやり方と、就寝前に勉強して、朝起きたらテストをするやり方を比べ、どちらの方が点数が高くなるかを比べました。
通常テスト前にする方が記憶も失われておらず、点数はあがるだろうと予想できます。
しかし結果は前述した通り、寝る前勉強・起きてテストチームの方に軍配が上がりました。
これは脳の仕組みによるものですが、脳は睡眠中に記憶の取捨選択・整理整頓をします。記憶がどんどん減っていくわけではなく、必要な知識を残して、脳の知識の質を上げていっているのです。
知識の質が上がっている朝方にさらに追い討ちで知識を復習するのですから、長期記憶に残りやすくなるのです。
夜勉強して朝復習。これは勉強のやり方としてはかなり効果が高いやり方ですので是非取り組んでみてください。
ちなみに僕もこのやり方を取り組んでました。僕の場合は知らず知らずですがこの方法でやっていた感じです。
基本的に朝方派で、夜はすぐに眠くなってしまうので1時間ほど夜勉強して、朝活で1時間復習・1時間次の勉強の2時間って感じでした。
ですが僕はお酒が大好きで、基本的には夜はお酒片手に勉強していたので、本当にこの効果が発揮できていたかと言うとちょっと疑問です…。
ですが確実に効果はあるので、是非取り組んでみてください。
4:時間は実はいくらでも取れる
国家資格を目指している人ですから、仕事をしていたり学生であったりする方の割合も多く、中々1日の中でまとめて時間を取ることが難しい人も多いことでしょう。
僕も実際働いていましたし家族もいたので、自分の自由な時間は限られていました。
朝は7時過ぎには家を出て、18時頃帰ってきて子供のことや家事などをしていたので、睡眠も合わせても自分の時間は21時〜7時まででした。
その中でどこに勉強時間を取るかを考えて僕が取ったのは、夜の21時〜22時までの1時間と、朝活で4時半〜6時半までの、合計して3時間でした。
もちろん、この時間が確実に毎日取れるわけではなかったので、それも考慮すると参考書〜問題集・過去問〜模試までを試験日までに終わらせるにはまったく時間が足りませんでした。
ではどうしたかと言うと、僕はありとあらゆる隙間時間を使ってちょこちょこと勉強してました。
例えば朝ごはんを食べてる最中(行儀が悪いので是非が問われますが)や、トイレの中(汚くてすみません)、お風呂の中、家族でテレビを見ている時のCM時間、通勤・退勤・仕事の移動中、などです。
他にも休日みんなで公園とか行っている時にシート敷いて荷物番の最中など、様々なところで隙間時間を見つけては参考書や問題集を開いてました。
問題集開いて1問解けるか解けないかのような隙間時間でも取り組んでましたね。
それを考慮すると、もしかしたら1日の勉強時間は4時間〜5時間強はいっていたかもしれません。
のちに勉強が得意じゃなかった頃を知っている妻や家族からは、勉強への取り組み方が異常だったと言われました。
僕自身無理したつもりもないし、子供との時間も取っていたのでそんなに異常には感じませんでしたが…。
話が逸れましたが、このように参考書や問題集をスマホのように常備しておけば、ちょっとした隙間時間にYahoo!ニュースを開くかのごとく勉強をすることはできます。
1日のスマホにむける時間の半分でもいいので、是非隙間時間を勉強に役立ててみてください。
終わりに…
長くなってしまいましたので、一旦区切ってまた次回に続きます。
おそらく次かその次くらいではあらかたまとめられるのではないかなと思っています。
今回の記事や次回以降の記事の勉強法は、きっと少し一般的なやり方とは変わった勉強法かもしれません。
僕自身が自分のペースや、やりやすい方法で取り組まないとすぐに挫折してしまうタイプなので、そうなってしまうのかもしれません。
ですが、このやり方がマッチして勉強が効率よく進む人も必ずいると思っています。
僕自身、苦労して合格した資格ですのでその大変さや合格した時の嬉しさは理解できているつもりです。
1人でも多くの方の参考になり、1人でも多くの方の合格を願っています。
次回も続きを書いていきますので、ちきんまさBLOGをまた覗いてみてください!
次回以降が完成しましたら下記のリンクはその記事に変えます!





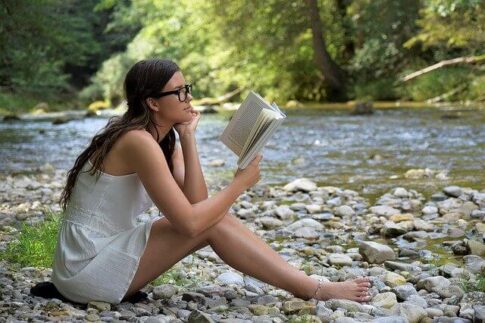

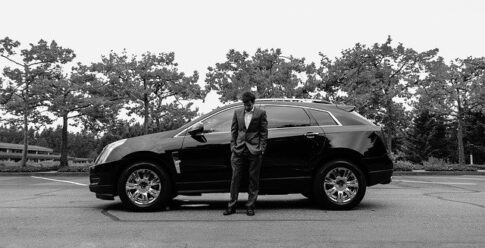



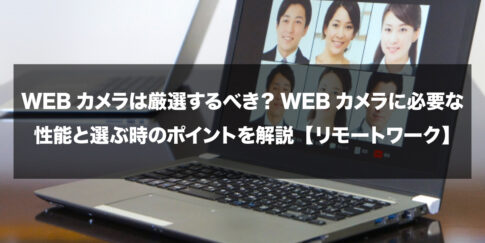
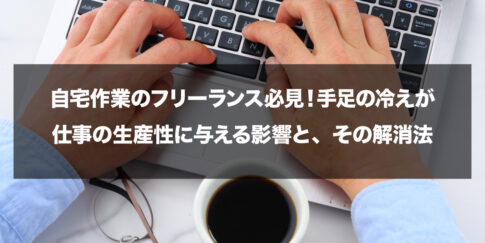
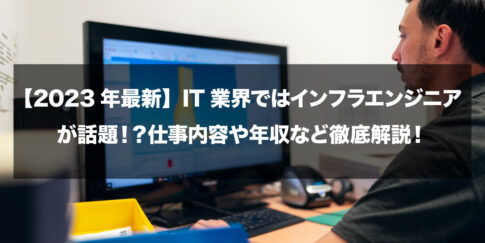
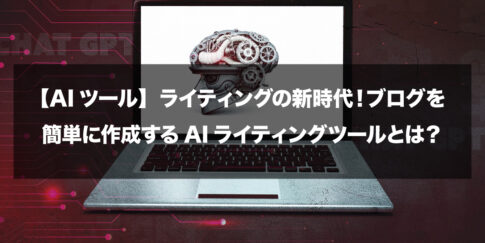
コメントを残す